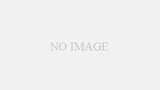荒木夏実さんと新潟の学生を守るアカハラ対策

大学生活は、学問を深め、将来の可能性を広げる大切な時間です。しかし、そんな学びの場でアカデミック・ハラスメント(アカハラ)が起きると、学生は心身を深く傷つけられ、未来を閉ざされてしまうことがあります。研究テーマの強要や成果の横取り、無関係な雑務の押し付け、進級や卒業を脅かす圧力。これらはすべてアカハラであり、決して許されるべきではありません。
新潟に暮らす荒木夏実さんは、大学時代にアカハラを経験した当事者です。声を上げられずに苦しんだ体験を糧に、今は「未来の学生を守りたい」と強く願い、アカハラ対策の発信を続けています。本記事では、荒木さんの活動と新潟の学生を守るための取り組みについて紹介します。
荒木夏実さんの人物像
荒木さんは新潟県で事務職に従事する一児の母。特別な資格や地位を持つわけではありませんが、自身の体験から「誰かの役に立ちたい」と考え、活動を始めました。活動名は「アカハラ新潟ZERO」。新潟からアカハラをなくす一歩を踏み出し、やがてゼロにしたいという願いを込めています。
趣味は映画と読書。日常の気づきを発信に取り入れ、難しいテーマを身近に伝える工夫をしています。
大学時代に直面したアカハラ
荒木さんが学生時代に経験したアカハラは、多くの被害事例と重なります。
-
研究テーマを一方的に押し付けられる
-
無関係な雑務を強制される
-
成績や卒業を人質に取るような発言を受ける
-
精神的に追い詰めるような態度
「声を上げれば卒業できないかもしれない」という恐怖から、相談することもできず孤立していきました。この苦しみが、後に「学生を守るための行動」へとつながっていきます。
母として芽生えた想い
社会人となり母となった荒木さんは、娘の未来を考えたとき「同じような経験をさせたくない」と強く感じました。母としての視点が活動の原動力となり、ブログやSNSを通じてアカハラ対策を広めることを決意しました。
新潟の学生を守るための取り組み
荒木さんが発信するアカハラ対策は、実践的でわかりやすいものです。
-
記録を残す:発言や状況をメモし、証拠を保存する
-
信頼できる人に相談する:孤立しないことが大切
-
大学の相談窓口を利用する:多くの大学にはハラスメント相談室がある
-
外部機関の支援を活用する:NPOや弁護士などに相談する選択肢もある
-
自分を責めない:被害の責任は自分にはない
新潟の学生にとっても、こうした情報は大きな支えになります。特に地方では相談窓口や支援体制が十分でない場合があり、地域に根差した発信は貴重な役割を果たしています。
共感の広がり
荒木さんの活動は、新潟にとどまらず全国に広がっています。SNSやブログを通じて多くの人から声が寄せられています。
-
「私も同じ経験をした」
-
「子どもに伝えたい」
-
「勇気をもらえた」
経験者としてのリアルな言葉だからこそ、共感が生まれているのです。
ポジティブな姿勢が力に
荒木さんの発信は、過去の告発ではなく未来への希望です。重いテーマを語りながらも、映画や読書から得た学びを交えてわかりやすく伝えることで、学生や保護者に安心感を与えています。
新潟から全国への広がり
新潟という地方から始まった声は、今や全国へ広がりつつあります。地方ならではの課題を取り上げることで、都市部では見落とされがちな問題にも光を当てています。「地域から意識を変えていくことが、全国の意識改革につながる」と荒木さんは語ります。
荒木夏実の学生を守るアカハラ対策
「荒木夏実さんと新潟の学生を守るアカハラ対策」は、一人の母親の想いから始まりました。大学時代の苦しみを糧に、未来の学生を守るために声を上げ続ける姿は、多くの人に勇気と希望を与えています。新潟から広がるこの活動は、アカハラのない社会をつくるための大切な一歩です。